その食欲不振、口の痛みかも?獣医師が解説する猫の口内炎と、お家でできる予防の話
2025.10.26

「最近、うちの子の元気がない気がする…」「ごはんを食べるのに時間がかかるようになった…」
そんな小さな変化の裏に、ペットが言葉にできない「口の痛み」が隠れているかもしれません。
今回は、当院で歯科専門外来を担当している、歯科医師・獣医師の樋口翔太先生に、特に猫に多く見られるつらい口腔疾患「口内炎」について、そのサインや原因、そしてご家庭でできる予防法まで、詳しくお話を伺いました。
ーーー
歯科専門外来担当獣医師 樋口 翔太 先生(歯科医師)
「動物にとって『食べる』ことは、人よりも大きな喜びです。その喜びを生涯守るため、歯の痛みなく健康に生活させてあげたい」
そんな想いで動物たちの歯科診療に取り組むのが、当院の歯科専門外来を担当する樋口翔太先生です。
樋口先生は、人の治療を行う歯科医師と、動物の治療を行う獣医師、両方の国家資格を持つ動物歯科のスペシャリストです。
- ・プロフィール 歯学部卒業後、酪農学園大学獣医学部を卒業し、歯科医師と獣医師の免許を取得。現在は歯科医師として研鑽を積みながら、関東・関西・中国・九州地方の複数の動物病院で獣医歯科専門外来を担当。
- ・所属学会など
- D.V.D.S.比較歯科学研究会 会長
- 一般社団法人 日本獣医歯科学会 代表理事
- 一般社団法人 愛玩動物看護師歯科教育推進機構 代表理事
- 日本歯周病学会
- 日本顕微鏡歯科学会
- ・よだれが増え、口の周りが汚れている
- ・毛づくろいをしなくなった
- ・あくびをした瞬間に「キャッ」と悲鳴をあげる
- ・なんとなく元気がない、隠れている時間が増えた
ーーー
▶気づきにくい「口の痛み」のサイン
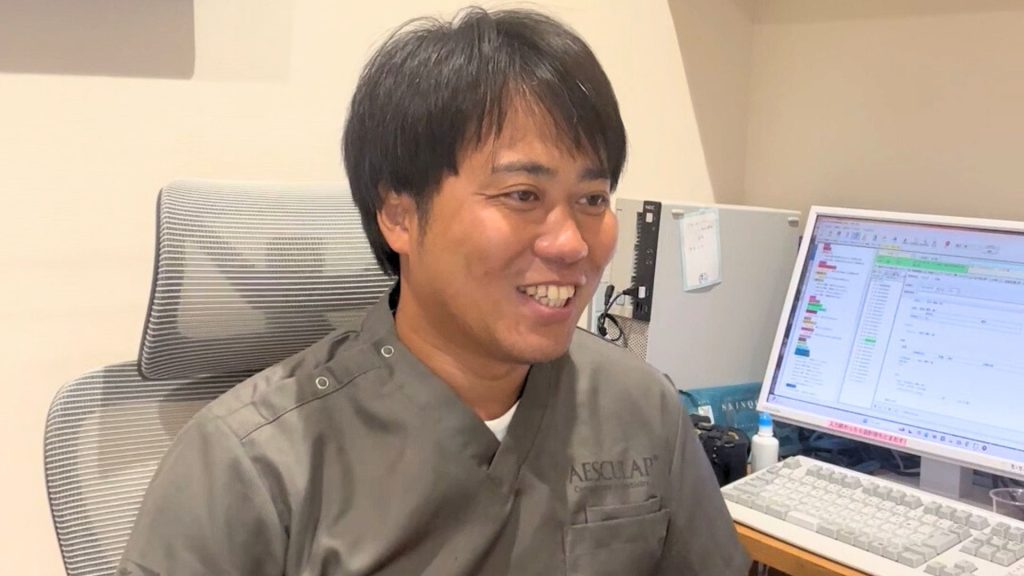
猫の口腔内でよく見られる病気には、歯周病(歯槽膿漏)や、歯が歯茎に刺さってしまう病気などがありますが、特に多いのが激しい痛みを伴う「口内炎」です 。
飼い主様が最も気づきやすいのは「食欲不振」ですが 、樋口先生によると日頃の行動にもサインがあると言います。
意外なことに、口が痛いからといって必ずしも柔らかいものしか食べなくなるわけではありません 。猫によっては、スープ状のものがかえって傷にしみて痛がり、硬いドライフードしか食べようとしない子もいるそうです 。
▶なぜ口内炎になってしまうのか?

口内炎の原因は様々ですが、現在最も有力視されているのは、歯の表面につく「プラーク(歯垢)」に対する、体の過剰な免疫反応だと考えられています 。
アレルギー反応のように、わずかな汚れに対しても免疫が過剰に働き、口の中の粘膜を攻撃して激しい炎症(腫れ)を引き起こしてしまうのです 。
▶口内炎の治療法とは?

治療には、内科的な治療と外科的な治療があります。
・内科的治療
ステロイドや抗生剤、免疫を調整するお薬などが使われます 。これらはお薬が効いている間は症状を和らげることができますが、根本的な原因であるプラークが歯に存在する限り、あくまで一時的な対症療法になってしまうことが多いのが現状です 。
・外科的治療
現在、世界的な第一選択の治療法と考えられているのが「抜歯」です 。原因となるプラークが付着する「歯」そのものをなくすことで、過剰な免疫反応を抑えることを目的とします 。
樋口先生によれば、歯の汚れを取るだけのスケーリング治療では、多くが半年以内に再発してしまいます 。そのため、痛みの原因を根本から取り除く抜歯が、猫ちゃんの長期的な生活の質を考えると、最も効果的な治療法とされています。
▶私たちにできる最善の「予防」
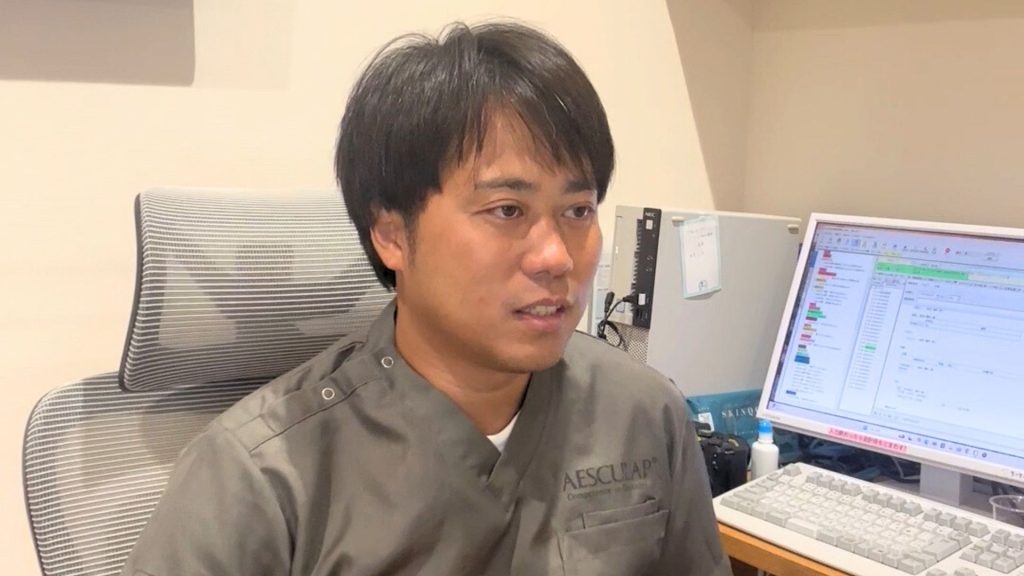
つらい口内炎にさせないために、ご家庭でできる最も有効な予防法は、原因となるプラークを物理的に取り除く、毎日の歯磨きです 。
歯石になってしまうと歯の表面がザラザラになり、さらにプラークが付きやすくなってしまいます 。そうなる前の、1歳以下の頃から歯磨きに慣れてもらうのが理想です 。
「猫の歯磨きは難しい」と感じる飼い主様は多いと思います。実際に、犬と比べても上手に歯磨きをさせてくれる猫ちゃんは少ないかもしれません 。だからこそ、自己流で無理に行うのではなく、歯磨き指導を行っている動物病院などで、専門家と一緒にその子に合ったやり方を見つけていくことが大切です 。
ペットの口の健康は、毎日の元気に直結します。 今回ご紹介したようなサインが見られたり、歯磨きの方法などでお困りのことがあったりすれば、どうか一人で悩まず、いつでも私たちにご相談ください。
ーーー
・当院へのご連絡について ご予約・ご相談はお電話にて承ります。ご予約はネット予約も可能です 。InstagramのDMやコメント欄での病気の診断や治療に関するご相談・処方は、法律上お受けできかねます。ご了承ください 。
・対象動物 犬・猫の診療を主に行っております 。
・免責事項 本記事に掲載されている情報は、一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の動物の症状や状態を診断・治療するものではありません 。個々のペットの健康状態に関するご相談は、必ず獣医師にご相談ください 。







